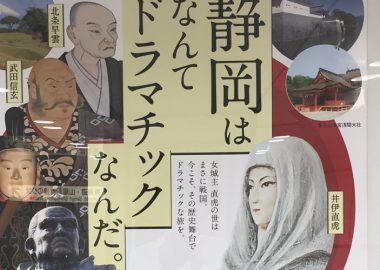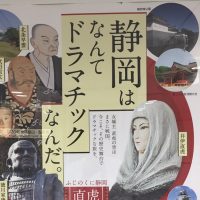なぜ「消えゆく灯」は10年後に注目の商店街になったのか?
「消えゆく灯」(1999年10月10日熊本日日新聞記事)と紹介された商店街が、10年後には約20万人の観光客が訪れる、活気あふれる商店街に変身した。阿蘇一の宮門前町商店街(熊本県阿蘇市)が変身した要因のキーワードは「30分間の滞在時間(どうすれば来た人が30分でも過ごせるようになるか)」。「イベントで365日の1日だけにぎわいを取り戻しても仕方がない」という共通認識の下で、商店街の各店が「知恵」「やる気」を「会議」で出し合った。
・店先に樹木を植えて木陰を造りベンチを設置。
・阿蘇からの豊富な湧き水を活かした「水基(みずき)」の設置により「水基巡り」を提案。
・地域の特産を使った商品(「馬ロッケ(馬肉コロッケ)」「サイダー」等)を各店が開発。
それらの推進を時間をかけて行い、次第に来訪者が増加し、滞在と回遊を楽しめる商店街としてのブランドを確立していった。商店街が提供できる価値が明確になったときに、活気がよみがえったのだ。
都市農村交流課 プロデューサー 石井和裕