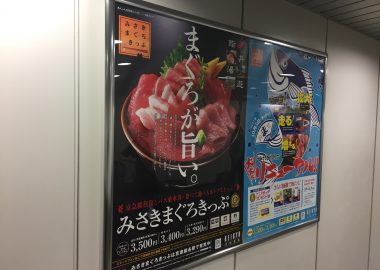世界遺産登録の本当の意味とは?
諮問機関がユネスコに対して、古代遺跡「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」を世界文化遺産へ登録するよう求める勧告をした。沖ノ島は「海の正倉院」と呼ばれる文化財の宝庫。沖ノ島は島自体が御神体となっており、沖ノ島から最も近い大島の「沖津宮遥拝(おきつみやようはい)所」(写真)から沖ノ島を拝む。
福岡県内では勧告当日の新聞の論調が「残念だ」になっていた。4遺産が登録対象から除外されたからだ。指定された沖ノ島は神の島で立ち入り禁止の私有地で観光客は入れない。つまり、沖ノ島以外の場所が除外されると観光客誘引の効果が限定的になるというのだ。しかし、世界文化遺産の本来の趣旨では観光効果は考慮されていない。「考古学的物証があり、普遍的価値があるモノ」を保護するために指定される。文化財保護は観光開発とは逆方向の活動。つまり、本当は世界文化遺産と観光とは相容れない面もあるのだ。実際のところ、世界文化遺産が最も話題になるのは登録のときであり、観光客の増加に効果的だとは限らない。過去の例を見ても、登録一年目の観光客は飛躍的に増加するが二年目に激減するケースがある。
とはいえ、地元では新聞の一面を飾ったように、大きな話題になっている。シンポジウムやイベントの開催回数も増えた。地域住民にとっては「地域が守ってきた宝が世界に認められた」大ニュースであることは間違えない。
世界文化遺産は地域資源を守る文化財保護と地域住民の誇りの醸成には大きな効果があるのだ。
都市農村交流課 プロデューサー 石井和裕

沖津宮遥拝所

沖津宮遥拝所

旧日本軍の砲台跡から水平線の沖ノ島方向を望む。