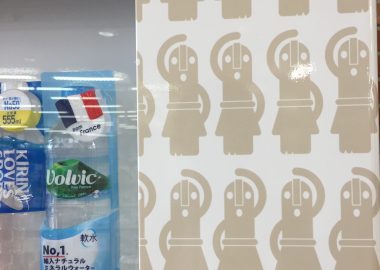消費者はブランドを市町村単位で考えるのか?
旅行会社へのヒヤリングをすると岩手県三陸地方と千葉県房総半島に意外な共通点が浮上した。いずれの地域も広大で、多くの市町村を包含しているが、それぞれの市町村の地域産品ブランドが、それほど強く独り立ちしていない。「三陸ブランド」「房総ブランド」として消費者からはイメージされているのだ。例えば女川町で採れる牡蠣は「女川の牡蠣」と呼ばれることが少なく「三陸の牡蠣」と呼ばれるケースが多い。南房総市の土産で有名な枇杷も「房総の枇杷」なのだ。中には、「気仙沼のふかひれ」「銚子のつり金目」といった例外はあるものの、多くの地域産品ブランドは「三陸の・・・」「房総の・・・」と認識される。つまり、この地域は自治体がブランド力を向上する競争をしながら、広域連携により広域地域ブランドを成長させていく必要がある。このようなケースを「競争的共存」と呼んでいる。当たり前のことだが、消費者は必ずしもブランドを市町村単位で考えるわけではないので、市町村間で顧客の奪い合いをしなければならないというルールは無い。
広域地域ブランドが根付いているのであれば、そのブランド力を活かして各自治体が共存し、同時に自治体間で競争をしていくと良い。
都市農村交流課 プロデューサー 石井和裕

三陸海岸特有の入り江の風景。

絶壁が海に面した房総半島の地形。